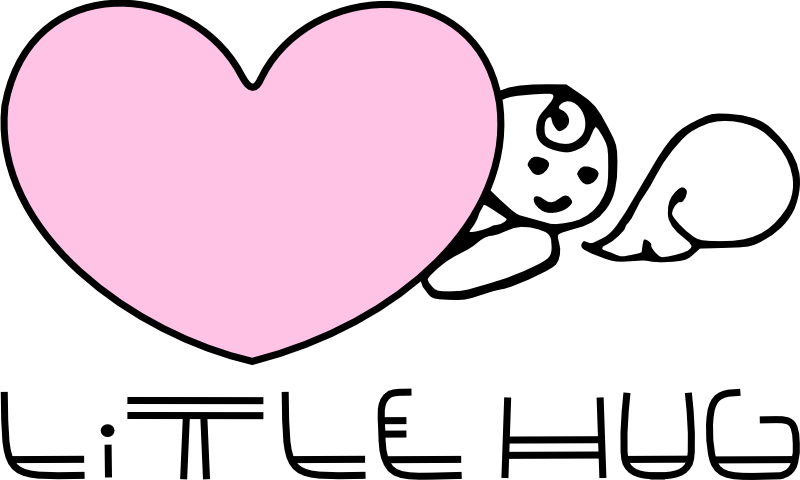「子どもを留守番させていいのは何歳から?」
「留守番中に、もしものことがあったらどうしよう…」
このような不安を感じる親御さまは少なくありません。近所のママ友から「うちは小学校1年生から大丈夫だったよ」と聞いても、自分の子どもを同じように留守番させていいか、迷ってしまうこともあるのではないでしょうか。
子どもの成長は一人ひとり異なり、留守番を始めるのに「何歳からOK!」という明確な決まりはありません。そして、留守番を安全に行うためには、年齢だけでなく子どもの性格や、親の事前準備がとても大切です。
この記事では「子どもは何歳から留守番できるのか」という目安と、安心して一人で過ごすために必要な準備を紹介します。あわせて、留守番が不安な場合に役立つ工夫や、親が頼れるサポート方法も解説。留守番させるときの親御さまの不安が少し和らぎ、子どもの成長へつながるきっかけになるでしょう。
子どもの留守番は何歳から可能なのか?

日本では「子どもを何歳から留守番させてよいか」という法律的な決まりはありません。つまり、年齢による一律の基準は設けられていないのです。では、実際に何歳から留守番を始める家庭が多いのでしょうか。
ベネッセ教育情報の調査によると「小学校1年生から留守番をさせた」という回答が26%と最も多い結果でした。その次に「小学校2年生から」という家庭が10%と多く、小学校低学年のタイミングで留守番を経験するケースが目立ちます。
一方で、未就学児のうちから短時間の留守番を経験させる家庭もあれば、小学生の高学年になるまで留守番を避ける家庭もあります。このように、スタート時期は家庭ごとにばらつきがあるのです。ただし、「何歳からOK!」と年齢だけで判断しないほうがいいでしょう。なぜなら子どもの理解力や性格によって、小学校低学年でも難しい場合もあれば、就学前でも可能なケースもあるからです。
留守番は何歳から?判断するポイントとは

「留守番をさせるのは、何歳からにしよう…」と、年齢にとらわれた考え方ではなく、子どもの心と体の成長を踏まえて判断するのが大切です。判断の基準として、以下の5つを目安に考えると良いでしょう。
| チェック項目 | 確認のポイント |
| 留守番を怖がっていないか | ・不安で泣いたりしない
・短時間の留守番を、問題なく過ごせる ・一人で過ごすことに抵抗がない |
| 緊急時の行動を理解しているか | ・地震、火事、不審者など「もしもの時」にどう対応すべきか理解している
・避難経路や集合場所を把握している |
| 基本的な生活能力 | ・トイレが自分でできる ・着替えができる ・軽食を自分で食べられる |
| 連絡手段を使えるか | ・親や祖父母へ連絡できる |
| ルールを守れるか | ・火を使わない ・外に出ない ・玄関のドアや窓を開けない |
チェック項目を確認し、親御さまや子どもに不安がある場合は、無理に留守番をさせないほうがよいでしょう。このように、一人で留守番させるのが不安な場合は、「リトルハグ」の英語ベビーシッターを利用してはいかがでしょうか。専門スタッフに預けられる安心感に加え、日常のやりとりを通じて自然に英語に触れられる環境も提供してくれます。
【リトルハグのサービス詳細はこちら】https://littlehug.co.jp/service/
何歳からOK?留守番前に親がすべき準備

ここでは、実際に留守番をさせるときに、親御さまが準備しておくと良いものを紹介します。安全に過ごせるように環境を整えることで、不安が少し軽くなるでしょう。
準備①:電話や来客へのルールを決める
家で留守番しているときの電話やインターホンの対応は、トラブルに直結する可能性が高いです。下記のようなルールを事前に決め、子どもに繰り返し伝えておきましょう。
- 知らない番号からの電話には絶対出ない
- 知っている人を名乗られても玄関を開けない
- インターホンは無視する
- 宅配便は不在票で対応する
練習としてロールプレイをすると、子どもの理解がより深まり落ち着いて行動できるでしょう。
準備②:転倒・ケガの原因を取り除く
留守番中は親の目が届かないため、ちょっとした不注意がケガにつながりかねません。
家の中の安全確認は入念に行うと良いでしょう。
- 床に物を置かない
- 浴槽や洗面所に水を張ったままにしない
- コンロの元栓をしめる
- 刃物や薬品を手の届かない場所に移す
このように、子どもが事故に遭わない工夫が大切です。
準備③:地震・火事のときの対応を話し合う
地震や火事は予測できず、突然起こる可能性が高いです。いざというときに慌てないためにも、事前に家族で行動の流れを確認しておきましょう。例えば「どの道を通って避難するか」「近所での集合場所はどこか」などを一緒に決めておくのも大切です。
また、非常持ち出し袋の場所を伝え、すぐに取り出せるようにしておくのも良いでしょう。
準備④:火を使わず食べられるものを用意する
留守番中でお腹がすいた時、子どもがコンロを使って料理をするのは非常に危険です。そのため、パンやおにぎり、果物や常温保存ができるお菓子など、火を使わずに食べられる物をあらかじめ用意しておきましょう。
また、冷蔵庫やテーブルに食べてよいものを分かりやすく置いておくと、子どもも迷わずに済みます。さらに、「この時間になったら食べていい」「お菓子は1つまで」などルールをあらかじめ伝えておくと、食べすぎを避けられるでしょう。
準備⑤:緊急連絡先を子どもと共有する
親の電話番号だけでなく、祖父母や近所の信頼できる人なども含めて、複数の連絡先を用意しておきましょう。スマホに登録しておくだけでなく、紙に書いて冷蔵庫に貼るなど、アナログな方法が役に立つ場合もあります。
また、連絡先を書くだけでなく、電話をかける相手の優先順位を決めておくと、子どもが迷わず行動できるでしょう。
留守番が心配なときにできる3つの対策

さまざまな準備をしても、やはり子どもに留守番をさせるのが不安な方もいらっしゃいます。そんな方に向けて、ここでは留守番が心配なときにできる対策を3つ説明します。
対策①:ホームセキュリティや防犯カメラを設置する
自宅に見守りカメラや警備システムを導入すると、離れていても子どもの様子を確認できます。録画機能や双方向の通話機能を備えた製品もあり、状況を把握しやすいのもメリットの一つ。
また、万が一のときに警備会社へ自動で通報できるよう備えておくと、子どもも親御さまも落ち着いて過ごせるでしょう。
対策②:ベビーシッターサービスを利用する
どうしても子どもを一人にさせるのが心配なら、ベビーシッターを利用するのも選択肢の一つです。ベビーシッターを頼めば、食事や遊び、学習のサポートをしてもらえるため、留守番も安心して任せられます。
特に「リトルハグ」の英語ベビーシッターなら、安心して子どもを預けられるだけでなく、日常の遊びや会話を通して英語に慣れるチャンスも広がります。厳選された外国人ベビーシッターが在籍し、保育に加えて送迎や家庭学習のサポートも可能。さらに、ピアノやスポーツといったレッスンを英語で行う教育シッティングにも対応しており、学習面に力を入れたい家庭にもおすすめです。
【リトルハグのサービス詳細はこちら】https://littlehug.co.jp/service/
対策③:学童保育などのサービスを利用する
学童保育は、自治体や学校が運営する公的なサービスで、小学生を対象に放課後や長期休暇中に利用できます。利用者数は年々増えており、共働き家庭だけでなく幅広く活用されているのが現状です。
子どもにとっても、友達と過ごせる環境があるため、一人で留守番するよりも孤独感も和らぐでしょう。
まとめ:子どもの留守番を見守る『リトルハグ』

留守番は「何歳から大丈夫」と年齢で一律に決められるものではありません。実際には、子どもの性格や理解力、生活スキルによって判断するのが現実的。電話や来客への対応、災害時の行動を理解できるか、トイレや着替えを自分でこなせるかが目安となります。
それでも不安が残る場合は、学童やベビーシッターといったサポートを組み合わせると良いでしょう。「リトルハグ」の英語ベビーシッターは、安全に子どもを預けられるだけでなく、日常生活を通じて自然と英語に触れられる魅力があります。安心感と教育的なメリットを兼ね備えたサービスとして、共働き家庭や英語教育を考える家庭におすすめです。
【リトルハグのお問合せはコチラ!】https://littlehug.co.jp/contact/